|
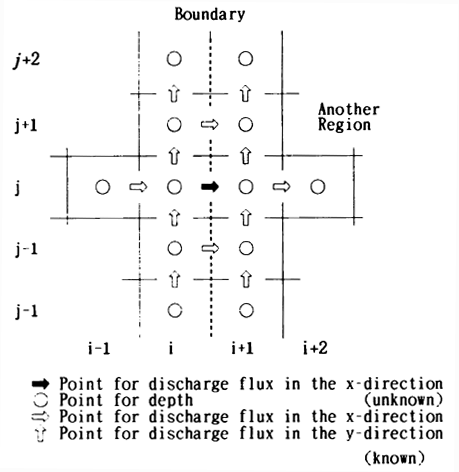
Fig-4 Points of variables for computed non-linear term
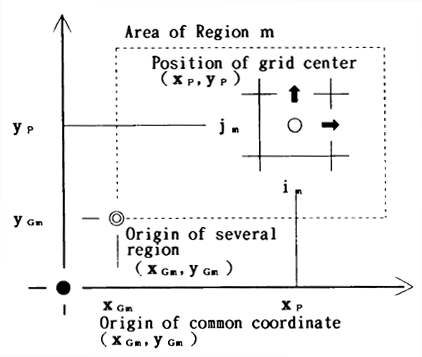
Fig-5 Coordinate system for grids in several regions
分散は1.46となり、7%程度計算値は過大であるが、経験的に提案されている許容誤差の範囲(幾何平均が0.8〜1.2程度、幾何分散が1.2〜1.6程度)に収まる。
次に、大阪湾システムによる昭和南海地震津波の追算結果の評価を行う。図-7は、相田(1981)モデルにより計算される紀伊水道・大阪湾沿岸の最大津波高の分布である。津波が大阪湾口を通過する過程で生じる回折・連破効果により、湾内の津波高は、紀伊水道内よりも小さくなる。そして、神戸から淡の輪までの湾奥で、浅水効果により増幅する。南海システムと同様に、図-7に表す紀伊水道から大阪湾の海岸沿いの最大津波高分布と痕跡高の分布を比較すると、分布傾向は良く再現され、幾何平均は1.06、幾何分散は1.22となり、計算値は60%程度過小であるが、計算誤差の許容範囲にある。
さらに、山陰システムにより、日本海中部地震津波の追算を行う。この計算の断層パラメータとして採用する相田(19831)モデル6)は、昭和南海地震と同様に、線形長波式による津波数値シミュレーションから断層パラメータを決定している。ただし、モデルの確定は、山陰沿岸ではなく、高い津波高の記録がある日本海東縁部(青森県から石川県の各沿岸)の痕跡高の再現を目標とした。本システムでも、事前に非線形計算による試行計算を行い、相田(1983)モデルの鉛直・水平変位量を1.23倍する修正断層モデルを最適条件と判断した。
図-8の左図は、修正モデルによる日本海伝播計算から推定される最大津波高分布である。津波高分布を見ると、波源域から日本海中央部の大和堆、隠岐、島根半島にかけて、津波高が帯状に高く、この帯状の海域は水深が浅い。相対的に浅い水深帯は、津波が屈折により集中し、津波エネルギーが捕捉され、高い津波高が発生する。
図-8の右図は、引き続く山陰沿岸の津波計算により推定される最大津波高分布である。日本海全域の津波高分布のうち、山陰沿岸の分布と良く一致し、境界からの入射波計算の妥当性が確認できる。浅海域の津波高分布見ると、複数の振動の山(津波高の大)と振動の節(津波高の小)が混在し、山と谷の距離から類推すると、周期5〜10分程度の振動系が形成される。
山陰海岸沿いの最大津波高と痕跡高の分布を比較すると、図-8の右図中のような沿岸分布が描かれる。両者の分布傾向及び津波高はほぼ一致し、幾何平均が0.94、幾何分散が1.50となり、計算値は6%程度過大であるが、計算誤差の許容範囲内にある。
3−2. 港湾別の津波計算値
前述した計算値と痕跡高の比較から明らかなように、広域津波計算の場合、計算値が過大・過小は海岸でまちまちである。そこで、港湾別に、計算値を痕跡高に近い値となるように補正係数を定め、これを利用する。補正係数は、幾何平均値が用いられ、線形長波の関係が成立すれば、港湾の津波高と断層のずれ量がほぼ比例関係にあるから、断層のずれ量に乗ずればよい。図-9は、補正後の須崎港における昭和21年当時の最大津波高の分布を表す。図中、陰影で計算浸水区域を表し、実線で表す浸水区域の現地調査結果と比較すると、計算の区域は、現地調査結果と良く一致する。また、図-10に大阪港における最大津波高分布を表す。計算される津波高は、相対的に窪んだ形状の海岸で大きくなる傾向がある。
前ページ 目次へ 次ページ
|